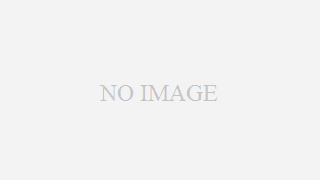 古文
古文 木曽の最後・平家物語1
木曽左馬頭、その日の装束には、赤地の錦の直垂に、
木曽左馬頭は、その日の衣装としては、赤地の錦の直垂に、
・木曽左馬頭(きそのさまのかみ) … 名詞
・そ …&en...
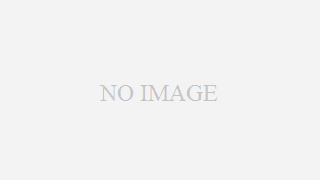 古文
古文 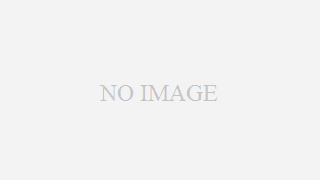 古文
古文 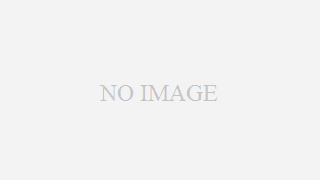 古文
古文 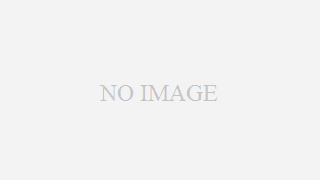 古文
古文 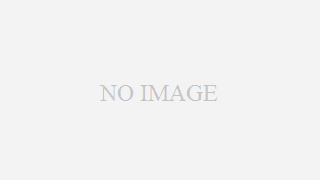 古文
古文 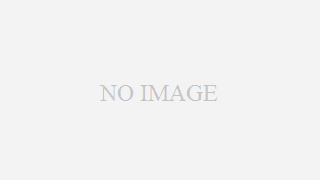 古文
古文 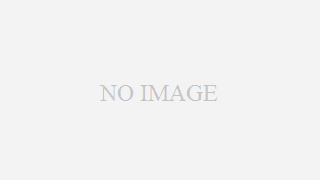 古文
古文 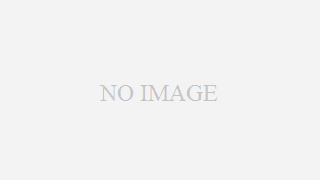 古文
古文 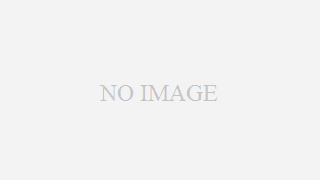 古文
古文 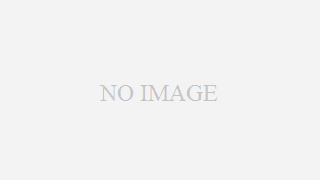 古文
古文 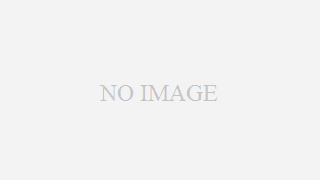 古文
古文 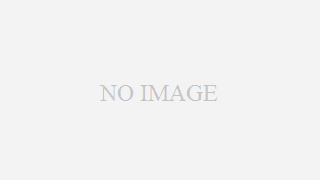 古文
古文